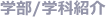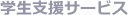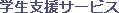дҪңжҘӯзҷӮ法科
ж•ҷиӮІиӘІзЁӢзҙ№д»Ӣ
| еҢәеҲҶ | ж•ҷ科еҗҚ | 1е№ҙз”ҹ | 2е№ҙз”ҹ | 3е№ҙз”ҹ | еҗҲиЁҲ | ||||||||||||||||||||||||
| 1еӯҰжңҹ | 2еӯҰжңҹ | 1еӯҰжңҹ | еӨҸеӯЈеӯЈзҜҖеӯҰжңҹ | 2еӯҰжңҹ | еҶ¬еӯЈеӯЈзҜҖеӯҰжңҹ | 1еӯҰжңҹ | 2еӯҰжңҹ | ||||||||||||||||||||||
| еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | еҚҳдҪҚ | жҷӮй–“(йҖұ) | ||||||||||||
| и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | и¬ӣзҫ© | е®ҹзҝ’ | ||||||||||||
| ж•ҷйӨҠ科зӣ® | еӨ§еӯҰз”ҹжҙ»гҒ®зҗҶи§Ј(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| еӨ§еӯҰз”ҹжҙ»гҒЁжңӘжқҘ(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| йҖІи·ҜеҸҠгҒіиҒ·жҘӯеҖ«зҗҶ(1)(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| еӨ§еӯҰе…ұйҖҡж•ҷйӨҠ(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| еҝғзҗҶеӯҰгҒ®зҗҶи§Ј | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| TOEIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡиғҪеҠӣ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| зӨҫдјҡеҘүд»• | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| е°ұиҒ·еҠӣйҮҸе®ҹеӢҷпјҸеүөжҘӯеҹәзӨҺ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ж•ҷйӨҠеҗҲиЁҲ | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | ||
| е°Ӯ攻科зӣ® | е°Ӯж”»еҝ…дҝ® | дҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰжҰӮи«– | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| и§Јеү–еӯҰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| з–ҫжӮЈеҲҘдҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®жҙ»еӢ• | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| е…җз«ҘдҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| дҪңжҘӯзҷӮжі•и©•дҫЎ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| зҘһзөҢзі»дҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| зІҫзҘһзӨҫдјҡдҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| иҮЁеәҠе®ҹзҝ’(3) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| е°ҸиЁҲ | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 6 | ||
| е°Ӯж”»йҒёжҠһ | еҢ»еӯҰз”ЁиӘһ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| з”ҹзҗҶеӯҰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| м•„лҸҷл°ңлӢ¬ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| е…җз«ҘзҷәйҒ”гғӘгғҸгғ“гғӘеӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ж©ҹиғҪи§Јеү–еӯҰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| иҮЁеәҠйҒӢеӢ•еӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| йҡңе®іе…җз«ҘгҒ®зҗҶи§Ј | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| зҘһзөҢи§Јеү–еӯҰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| зҗҶеӯҰзҡ„жӨңжҹ»еҸҠгҒіе®ҹзҝ’ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| йҒӢеӢ•гғӘгғҸгғ“гғӘеӯҰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| дҪңжҘӯйҒӮиЎҢеҲҶжһҗ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| иЈңеҠ©еҷЁеӯҰеҸҠгҒізҫ©иӮўеӯҰ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| зӣёи«ҮеҝғзҗҶеӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| иҮЁеәҠзҘһзөҢеӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| зҘһзөҢ科еӯҰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| дҪңжҘӯзҷӮжі•йҒ“е…·еҸҠгҒіе®ҹзҝ’ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| еҡҘдёӢйҡңе®ідҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ж„ҹиҰҡеҮҰзҗҶйҡңе®ігҒЁд»ІиЈҒ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| зІҫзҘһеҒҘеә·жҰӮи«– | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| з ”з©¶ж–№жі•и«– | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| иҮЁеәҠе®ҹзҝ’(1) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ж„ҹиҰҡгғӘгғҸгғ“гғӘзҸҫе ҙе®ҹзҝ’ | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| иҮЁеәҠе®ҹзҝ’(2) | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| зӯӢгғ»йӘЁж јзі»дҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| зҘһзөҢзі» дҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ(2) |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ж„ҹиҰҡгҒЁиӘҚзҹҘгғӘгғҸгғ“гғӘ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ең°еҹҹзӨҫдјҡгғӘгғҸгғ“гғӘ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| гӮ№гғ—гғӘгғігғҲиЈҪдҪң | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| дҪңжҘӯзҷӮжі•зү№и«–(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| дҪңжҘӯзҷӮжі•зү№и«–(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| е…җз«ҘжӨңжҹ»еҸҠгҒіи©•дҫЎ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| иҖҒдәәдҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| иЈңеҠ©е·ҘеӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| дҪңжҘӯзҷӮжі•гӮ»гғҹгғҠгғј | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| иҮЁеәҠдәӢдҫӢз ”з©¶ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| е…¬иЎҶдҝқеҒҘеӯҰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| еҢ»зҷӮжі•иҰҸ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| е°ҸиЁҲ | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 5 | 0 | 10 | 14 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0 | 87 | 65 | 29 | ||
| е°Ӯж”»еҗҲиЁҲ | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 14 | 17 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0 | 112 | 86 | 35 | ||
| еҗҲиЁҲ | ж•ҷйӨҠеҗҲиЁҲ | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 1 | |
| е°Ӯж”»еҗҲиЁҲ | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 14 | 17 | 13 | 4 | 15 | 15 | 0 | 112 | 86 | 35 | ||
| ж•ҷ科з·ҸиЁҲ | 20 | 20 | 0 | 21 | 19 | 2 | 22 | 16 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 7.0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 4 | 16 | 16 | 0 | 130 | 100 | 36 | ||
ж•ҷ科зӣ®жҰӮиҰҒ
дҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰжҰӮи«–в… ,в…Ў
зҸҫеңЁгҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®зҸҫзҠ¶гҖҒдҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®йҒҺзЁӢеҸҠгҒіеҲҶжһҗгҒЁжІ»зҷӮеҶ…е®№гҒ«й–ўгӮҸгӮӢдҪңжҘӯзҷӮжі•гӮ’зҙ№д»ӢгҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дәәдҪ“и§Јеү–еӯҰеҸҠгҒіе®ҹзҝ’
дәәгҒ®еӢ•гҒҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиә«дҪ“ж§ӢйҖ гҒ®йҒӢеӢ•еӯҰзҡ„еҪ№еүІгҖҒж©ҹиғҪгҖҒз”ҹзҗҶеҸҠгҒіз”ҹеҠӣеӯҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒ—гҖҒеӢ•зҡ„йҒӢеӢ•еӯҰгҖҒй–ўзҜҖйҒӢеӢ•еӯҰгҖҒйҒӢеӢ•з”ҹзҗҶгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶з§‘зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
з”ҹзҗҶеӯҰ
зҙ°иғһгҖҒзө„з№”гҖҒеҗ„еҷЁе®ҳгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁж©ҹиғҪгӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®з”ҹзҗҶеӯҰзҡ„ж©ҹеҲ¶гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒз–ҫз—…гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁеҢ»еӯҰзҡ„з®ЎзҗҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе№…еәғгҒҸзҹҘиӯҳгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дҪңжҘӯйҒӮиЎҢеҲҶжһҗеҸҠгҒіе®ҹзҝ’
дҪңжҘӯзҷӮжі•гӮ’жӮЈиҖ…гҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гҒӣгӮӢйҡӣгҖҒеҗ„еҖӢдәәгҒ«еҗҲгҒЈгҒҹзӣ®зҡ„гҒ®гҒӮгӮӢдҪңжҘӯгӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁдҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®е°Ӯй–Җз”ЁиӘһиӘ¬жҳҺгҖҒжІ»зҷӮеҺҹеүҮгҖҒдҪңжҘӯеҲҶжһҗгҖҒдҪңжҘӯж–№жі•гҒЁжқҗж–ҷйҒёжҠһгҒӘгҒ©гӮ’з ”з©¶гҒҷгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹдҪңжҘӯгҒӢгӮүжІ»зҷӮгҒ«еӨүеҪўгҒ•гҒӣгӮӢйҒҺзЁӢгҒЁеӨүеҪўгҒ•гҒӣгӮӢзҗҶз”ұгҒӘгҒ©гӮ’з ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
ең°еҹҹзӨҫдјҡдҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ
ең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ§гҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒЁең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ§гҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®жҺҘиҝ‘ж–№жі•гӮ’зҝ’еҫ—гҒҷгӮӢгҖӮ
е…җз«ҘдҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ в… ,в…Ў
зҷәйҒ”йҡңе®іе…җз«ҘгҒ®иЎҢеӢ•зү№жҖ§зҗҶи§ЈгҖҒйҡңе®іе…җз«ҘгҒ®ж©ҹиғҪж°ҙжә–и©•дҫЎеҸҠгҒіжІ»зҷӮиЁҲз”»иЁӯе®ҡгҖҒйҡңе®іе…җгҒ®ж©ҹиғҪеҗ‘дёҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•гҖҒзҸҫе ҙе®ҹзҝ’гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиҮЁеәҠзҡ„зҹҘиӯҳгҒЁзөҢйЁ“зҝ’еҫ—гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰйҡңе®іе…җз«ҘгҒ®жІ»зҷӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәӢй …гӮ’еӯҰгҒ¶з§‘зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еӢ•дҪңзҗҶи«–еҸҠгҒіе®ҹзҝ’
еҝғзҗҶгғ»зІҫзҘһзҡ„з–ҫжӮЈгҖҒе°Ҹе…җгҒ®з–ҫжӮЈгҖҒи„іжҖ§йә»з—әгҒӘгҒ©гҒ®з–ҫжӮЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒе®ҡзҫ©гҒЁиЁәж–ӯгҖҒи©•дҫЎгҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢзҘһзөҢеӯҰзҡ„гҖҒж•ҙеҪўеӨ–科зҡ„гҖҒй–ўзҜҖеӯҰзҡ„ж©ҹиғҪеӣһеҫ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•ж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иҮЁеәҠдҪңжҘӯзҷӮжі•и©•дҫЎ
е®ҹзҝ’гӮ’йҖҡгҒ—гҒҹжӮЈиҖ…гҒ®и©•дҫЎжҠҖиЎ“гӮ’еҗ«гӮҒгҒҹдҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®йҒҺзЁӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢ科зӣ®гҒ§гҖҒйҒӢеӢ•иӘҝзҜҖгҖҒиҰ–иҰҡжҗҚеӮ·гҖҒж„ҹиҰҡгҖҒзҹҘиҰҡеҸҠгҒіиӘҚзҹҘжҠҖиЎ“гҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҝғзҗҶзӨҫдјҡзҡ„ж©ҹиғҪеӣһеҫ©гҒӘгҒ©гӮ’з ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
зІҫзҘһзӨҫдјҡдҪңжҘӯзҷӮжі•
зІҫзҘһдҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӮЈиҖ…жІ»зҷӮж–№жі•еҸҠгҒійҒ©з”Ёж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
зҘһзөҢзі»дҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰеҸҠгҒіе®ҹзҝ’ в… ,в…Ў
и„іеҚ’дёӯгҖҒеӨ–еӮ·жҖ§и„іжҗҚеӮ·гҖҒйҖҖиЎҢжҖ§зҘһзөҢз–ҫжӮЈгҖҒзҘһзөҢеҺҹжҖ§ж©ҹиғҪйҡңе®ігҖҒзӯӢеҺҹжҖ§ж©ҹиғҪйҡңе®ігҖҒжң«жўўзҘһзөҢзі»з–ҫжӮЈгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҪңжҘӯзҷӮжі•еҸҠгҒійҒ©з”Ёж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
йҒӢеӢ•жІ»зҷӮеӯҰеҸҠгҒіе®ҹзҝ’
жІ»зҷӮзҡ„йҒӢеӢ•гҒҜгҖҒзҘһзөҢзі»гҒЁзӯӢиӮүзі»еҸҠгҒій–ўзҜҖзі»гҒ®йқһжӯЈеёёзҡ„гҒӘж©ҹиғҪгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҹж©ҹиғҪзҡ„жҙ»еӢ•гӮ’жӯЈеёёзҠ¶ж…ӢгҒ«еҸ–гӮҠжҲ»гҒҷгҒҹгӮҒгҒ®жІ»зҷӮж–№жі•гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒж©ҹиғҪзҡ„дҪңжҘӯгҒ®йҒӮиЎҢгҖҒзӣ®зҡ„гҒ®гҒӮгӮӢжҙ»еӢ•гҒӘгҒ©гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹжІ»зҷӮж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е…¬иЎҶдҝқеҒҘеӯҰ
еҒҘеә·гҒ®з¶ӯжҢҒеҸҠгҒіеў—йҖІгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒз’°еўғз–ҫжӮЈгҒ®дәҲйҳІж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶з§‘зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еҢ»зҷӮжі•иҰҸ
дҝқеҒҘеҢ»зҷӮжі•иҰҸгҒ®еҶ…е®№гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒйҒөе®ҲгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҝқеҒҘй–ўдҝӮгҒ®еҢ»зҷӮжі•иҰҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢ
иҮЁеәҠе®ҹзҝ’
зҸҫе ҙиҰӢеӯҰгҒЁз—…йҷўгҒ§гҒ®иҮЁеәҠе®ҹзҝ’гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰж•ҷиӮІзҗҶи«–гҒЁе®ҹйҡӣгӮ’иӘҝе’ҢгҒ•гҒӣгҒҰгҖҒиҮЁеәҠгҒ§дҪңжҘӯзҷӮжі•гӮ’ж–ҪгҒҷе°Ӯй–ҖдҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иіҮиіӘгӮ’йӨҠгҒҶзӣ®зҡ„гҒ§гҖҒгғӘгғҸгғ“гғӘз—…йҷўгҖҒз·ҸеҗҲз—…йҷўгҒӘгҒ©гҒ§иҮЁеәҠе®ҹзҝ’гӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҖӮ
зҘһзөҢи§Јеү–еӯҰеҸҠгҒіе®ҹзҝ’
зҘһзөҢи§Јеү–еӯҰгҒЁгҒҜдҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®жҺҘиҝ‘ж–№жі•гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘ科зӣ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒи„ігҒ®еӨ–йғЁж§ӢйҖ гҖҒй«„иҶңеҸҠгҒіи„іи„Ҡй«„ж¶ІгҖҒиЎҖж¶ІдҫӣзөҰеҸҠгҒізҘһзөҢзі»гҒ®зҷәйҒ”гҖҒгҒқгҒ—гҒҰи„Ҡй«„гҖҒи„іе№№гҖҒиҒҙиҰҡзі»гҖҒеүҚеәӯзі»гҖҒи„ізҘһзөҢгҖҒе°Ҹи„ігҖҒиҰ–еәҠгҖҒиҰ–иҰҡзі»гҖҒиҮӘеҫӢзҘһзөҢзі»гҖҒзҘһзөҢдјқйҒ”зү©иіӘгҖҒеӨ§и„ізҡ®иіӘгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иҮЁеәҠзҘһзөҢеӯҰ
иҮЁеәҠзҘһзөҢеӯҰгҒҜзҘһзөҢи§Јеү–еӯҰгҒ®зҹҘиӯҳгӮ’еҹәгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®з–ҫжӮЈгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҘһзөҢеӯҰзҡ„гҒӘе…ЁдҪ“зҡ„жҺҘиҝ‘еҸҠгҒіиҮЁеәҠзҡ„жҺҘиҝ‘гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢ科зӣ®гҒ§гҖҒж„Ҹиӯҳйҡңе®ігҖҒи„ізҘһзөҢжӨңжҹ»гҖҒиҰ–иҰҡеҸҠгҒійҒӢеӢ•жҗҚеӮ·йҡңе®ігҖҒдҪ“еҲ¶ж„ҹиҰҡйҡңе®ігҖҒи„ҠжӨҺжҗҚеӮ·гҖҒи„іеҚ’дёӯгҖҒеӨ–еӮ·жҖ§и„іжҗҚеӮ·гҒӘгҒ©гӮ’еӯҰгҒ¶з§‘зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
з—…зҗҶеӯҰ
дҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®жҺҘиҝ‘ж–№жі•еҸҠгҒійҒ©з”Ёж–№жі•гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢ科еӯҰзҡ„зҗҶи§ЈгҒ«еҪ№з«ӢгҒӨгӮҲгҒҶз–ҫз—…гҒ®еҺҹеӣ гҒЁзҷәз”ҹж©ҹеҲ¶еҸҠгҒійҖІиЎҢйҒҺзЁӢгҖҒиә«дҪ“гҒ«еҸҠгҒјгҒҷеҪұйҹҝгҒӘгҒ©гҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘжҰӮеҝөгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒзҙ°иғһжҗҚеӮ·еҸҠгҒіз–ҫз—…гҖҒзӮҺз—ҮгҒЁжІ»зҷ’гҖҒж„ҹжҹ“жҖ§з–ҫжӮЈгҖҒе…Қз–«жҖ§з–ҫжӮЈгҖҒж–°з”ҹзү©еҪўжҲҗз–ҫжӮЈгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
ж©ҹиғҪи§Јеү–еӯҰеҸҠгҒіе®ҹзҝ’
ж©ҹиғҪи§Јеү–еӯҰгҒҜгҖҒи©ігҒ—гҒ„и§Јеү–еӯҰзҡ„зҹҘиӯҳеҸҠгҒіеӣӣиӮўгҒЁи„ҠжӨҺгҒ®ж©ҹиғҪгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘдёҖжҷӮзҡ„гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдҝқйҡңзҡ„гҒӘеӢ•гҒҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзӯӢйӘЁж јзі»ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғӘгғҸгғ“гғӘеҢ»еӯҰ
дҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„жӮЈиҖ…гҒ®ж©ҹиғҪи©•дҫЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒд»–гҒ®й ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҺҘиҝ‘ж–№жі•гҒЁиӘІзЁӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶з§‘зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иЈңеҠ©еҷЁе…·еҸҠгҒізҫ©иӮўеӯҰ
еҷЁе…·гҖҒз’°еўғгҖҒжҙ»еӢ•гҒ«йҒ©еҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәзӨҺзҡ„дҪңжҘӯзҷӮжі•жҠҖиЎ“гҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪңжҘӯжҙ»еӢ•гҒӘгӮүгҒігҒ«иҮӘе·ұз®ЎзҗҶгҖҒйҒҠгҒіеҸҠгҒідҪҷжҡҮжҠҖиЎ“гӮ’зҝ’еҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘиЈңеҠ©еҷЁе…·еҸҠгҒізҫ©иӮўгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҒиЈҪдҪңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶з§‘зӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дҝқеҒҘзөұиЁҲ
дҪңжҘӯзҷӮжі•й ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе®ҹйЁ“еҸҠгҒіиҖғеҜҹз ”з©¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®зөұиЁҲзҡ„жҰӮеҝөеҸҠгҒіж–№жі•гғ»зҗҶи§ЈгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰзөҗжһңгҒ®еҲҶжһҗгҖҒи«–зҗҶзҡ„жұәе®ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дҪңжҘӯзҷӮжі•гӮ»гғҹгғҠгғј
гҒ“гҒ®иӘІзЁӢгҒ§гҒҜ иҮЁеәҠгҒ§гҒ®е®ҹйҡӣгҒ®дҪңжҘӯзҷӮжі•дәӢдҫӢгӮ’еӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§жІ»зҷӮйҒҺзЁӢгҒ®зҗҶи§ЈгӮ’еҠ©гҒ‘гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еҹәгҒ«дҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®зҸҫеңЁгҒ®еӢ•еҗ‘еҸҠгҒіжІ»зҷӮж–№жі•гҖҒгҒҫгҒҹз ”з©¶ж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҝ’еҫ—гҒҷгӮӢгҖӮ
иҖҒе№ҙеӯҰ
иҖҒе№ҙжңҹгҒ®иә«дҪ“зҡ„зү№еҫҙгҒЁиҖҒеҢ–йҒҺзЁӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒиҖҒдәәгҒ®ж©ҹиғҪдҝғйҖІгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®иҖҒдәәз–ҫжӮЈгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдҪңжҘӯзҷӮжі•еҸҠгҒійҒ©з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶гҖӮ
иЁҖиӘһжҢҮе°Һ
иЁҖиӘһгҒ®ж§ӢйҖ еҸҠгҒіиӘӯи§Јж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®зҗҶи§ЈгӮ’еҹәгҒ«гҖҒзҷәйҹігҖҒеҚҳиӘһгҖҒдјҡи©ұж–№жі•гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҲҶжһҗеҸҠгҒіжІ»зҷӮж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дәәй–“иЎҢеӢ•гҒЁзӨҫдјҡз’°еўғ
йҡңе®іе…ӢжңҚгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зҗҶи«–еҸҠгҒіжҠҖиЎ“гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹзӨҫдјҡжҙ»еӢ•гҒ®жӨңжҹ»гҖҒеҲҶжһҗгҖҒеҜҫдәәй–ўдҝӮжҠҖиЎ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иҮЁеәҠйҒӢеӢ•еӯҰ
дәәдҪ“йҒӢеӢ•гҒ®е№ҫдҪ•еӯҰзҡ„жҖ§иіӘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶гҖӮ
家ж—ҸзҰҸзҘүи«–
家ж—ҸжІ»зҷӮгӮ’еәғзҜ„еӣІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжӯҙеҸІгҖҒдёҖиҲ¬е®¶ж—Ҹз’°еўғгҖҒ家ж—ҸжІ»зҷӮгҒ®жҰӮеҝөгҖҒиҮЁеәҠдәӢдҫӢгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дҝқиӮІе®ҹзҝ’
дҝқиӮІе®ҹзҝ’гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰеӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ®дҝқиӮІиЁ“з·ҙгҒ®ж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз ”з©¶гҒҷгӮӢеӯҰе•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
еҘүд»•жҙ»еӢ•
дҪңжҘӯзҷӮжі•й–ўйҖЈж–ҪиЁӯгҒ«еҘүд»•жҙ»еӢ•гҖҒиҰӢеӯҰгҒӘгҒ©гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒдҪңжҘӯзҷӮжі•гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢдәәгҒҹгҒЎгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒдҪңжҘӯзҷӮжі•гҒ®еҪ№еүІгӮ’еӯҰгҒігҖҒжӯЈгҒ—гҒ„дҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒЁгҒ—гҒҰеӮҷгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚеҹәжң¬зҡ„гҒӘеҝғж§ӢгҒҲгӮ’еӯҰгҒ¶гҖӮ
иӘҚзҹҘгғӘгғҸгғ“гғӘ
и„ігҒ®ж§ӢйҖ гҒЁиӘҚзҹҘж§ӢйҖ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒігҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢж©ҹиғҪжҗҚеӮ·гҒ®и©•дҫЎгҒЁиӘҚзҹҘгғӘгғҸгғ“гғӘзҷӮжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶гҖӮ
еҡҘдёӢйҡңе®ідҪңжҘӯзҷӮжі•еӯҰ
еҡҘдёӢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи§Јеү–еӯҰзҡ„ж§ӢйҖ еҸҠгҒіеҡҘдёӢгҒ®ж®өйҡҺгӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҖҒеҡҘдёӢйҡңе®ігҒ®е•ҸйЎҢгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢгғӘгғҸгғ“гғӘжҠҖиЎ“еҸҠгҒіиЈңе„ҹжҲҰз•ҘгӮ’еӯҰгҒігҖҒз—ҮзҠ¶еҲҘзҷӮжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰгҒ¶гҖӮ